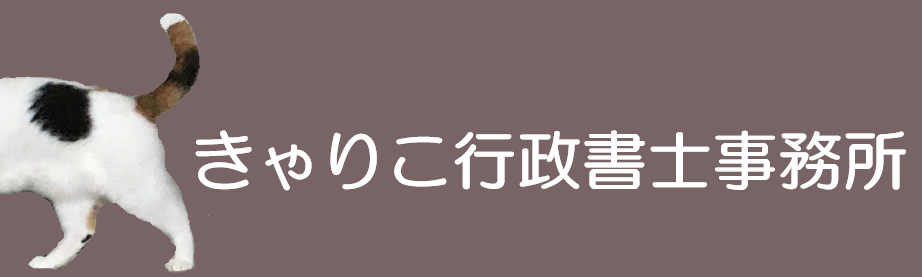成年後見制度について
成年後見制度とは、認知症や障がいによって、ひとりで物事を決めること(判断能力)に不安・心配がある人の、色々な契約や手続きのお手伝いをする制度です。
成年後見制度には2つの種類があります。
| 任意後見制度 | 法定後見制度 |
| 将来どんなお手伝いを受けるのかを本人が決めることができる制度です。 誰にお手伝いを受けるのか、自分で選ぶことができます。 (任意後見受任者、任意後見人) | すでに判断能力が不十分な方が必要なお手伝いを受けられる制度です。 4親等内の親族等の申立により家庭裁判所が後見人等を選びます。 (成年後見人、保佐人、補助人) |
お手伝いをする人(後見人等)には、できることとできないことがあります 。
| 後見人等にできること | 後見人等にできないこと |
| 【財産管理】 保険料や税金の支払い お金の出し入れのお手伝い 【身上保護】 日常の色々なサービスの契約手続きのお手伝い (介護・福祉のサービス、食事・掃除・買い物のサービスなど) 入院・施設入居の手続きのお手伝い 定期的な状況確認の連絡・住まいへの訪問 | 入院・手術をするしないを決めること 身元保証人や入院保証人になること 食事・掃除・買い物・介護などのお世話を実際にすること 生活に必要な食品や日用品を買うときの同意・取消 |
任意後見制度
十分な判断能力があるうちに、将来の判断能力が不十分な状態になるときに備えて、 あらかじめ自分で選んだ人(任意後見人)に、自身の生活、療養看護や財産管理に関する事務について権限を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書で結んでおく制度です。
任意後見契約をしておくことで、判断能力が低下したときは、 任意後見人が、契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をします。
「生前事務委任契約・死後事務委任契約」を併用するケースが多いです。
| 生前事務委任契約 | 死後事務委任契約 |
| 判断能力があるけれど、ご自身で対応できない・身の回りのお世話をしてくれる親族が近くにいないとき、 どんなお手伝いをしてほしいか決めておく契約です。 | ご自身が亡くなった後の事務手続きを任せられる親族が近くにいない・親族の負担を減らしたいとき、 どんなお手伝いをしてほしいか決めておく契約です。 |
| 生前事務委任契約でできること | 死後事務委任契約でできること |
| 介護・福祉のサービス利用契約 病院などの入退院手続き 日常生活の各種支払い 現金・預貯金通帳・不動産の管理 など | 死亡届の届出人になること 葬儀・納骨などに関する手続き 医療施設・介護施設などの料金精算 戸籍や年金について、役所などへの届け出 公共料金・携帯電話・インターネット・賃貸物件の解約手続き 親族、友人、知人への連絡 お住まいに残った家財の処分 など |
法定後見制度
すでに判断能力が不十分な状態である場合に、個別事情に応じて家庭裁判所が適切な援助者(補助人・保佐人・後見人いずれか)を選び、援助者が本人の支援を行う制度です。
補助人
判断能力が不十分な方 本人の意向に沿って、重要な法律行為の一部について、同意や、取り消しをして(同意権・取消権)、本人を支援します。
本人の同意により、特定の法律行為について代理権が付与されたときは、本人の意思を尊重しながら本人に代わって契約を結ぶこともできます。
保佐人
判断能力が著しく不十分な方 金銭の貸借や、不動産の売買など一定の重要な法律行為について、同意や、取り消しをして(同意権・取消権)、本人を支援します。
本人の同意により、特定の法律行為について代理権が付与されたときは、本人の意思を尊重しながら本人に代わって契約を結ぶこともできます。
後見人
判断能力が欠けているのが通常の状態の方 本人に代わって、いろいろな契約を結んだり、財産を管理し(代理権)、 もし本人に不利益となる契約や財産の処分などが行われた場合には、それを取り消すなどして(取消権)本人が日常生活に困らないよう支援をします。
後見人等への報酬支払いについて
| 任意後見制度 | 法定後見制度 |
| 委任者と受任者が契約をする時に金額や支払方法を決めます 毎月末ごとに支払う方法が多いです | 後見人等が報酬付与の申立をして、家庭裁判所が審判により報酬の金額を決定します 年に1回、家庭裁判所への定期報告時期に、本人の財産から支払いとなります |
■任意後見・法定後見どちらも月額 2 万円~が相場となっています
■任意後見契約書を公証人が作成するときに支払う手数料があります
■契約書の起案や必要な書類の取得を依頼すると、別に報酬がかかります
■任後見監督人が選ばれたときは、別に報酬がかかります