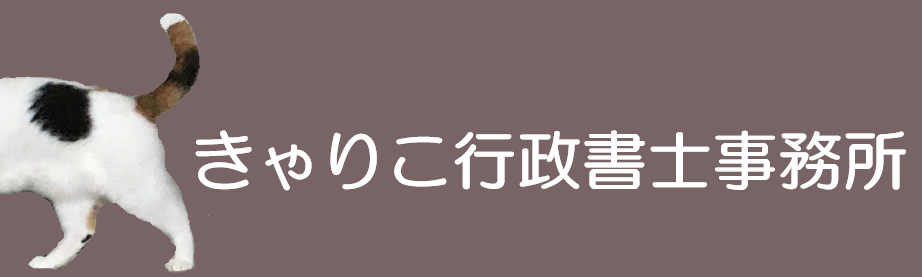愛する人、大事なペットのお世話をしてくれる人にだけ財産を残したい
揉めごとのあった戸籍上の家族にはできるだけ相続をさせたくない
急に家族が亡くなり、遺言書も手元になく、
時間的・精神的な余裕がない中で、相続の手続をどうすれば良いか困っている
そんな方のお手伝いがしたいです。
自筆証書遺言の作成サポート
「自筆証書遺言」とは、遺言者が紙に、遺言の内容全文・日付・氏名を手書きし、署名の下に押印して作成するものです。
遺言の内容とは、「誰に 何を 相続させる(遺贈する)」のかということです。
これらの項目を、手書きではなく、パソコンなどで記載すると、無効になってしまいます。
なお、民法の改正により、財産に関する資料(財産目録)は手書きでなくても有効になりました。
例)財産目録をパソコンで作成・預金通帳のコピーや不動産登記事項証明書を添付するなど
この場合、これらの財産目録のページごとに、遺言者の署名・押印が必要です。
自筆証書遺言は、自宅などで保管する場合、遺言者死亡後に相続人などに発見されたとき、家庭裁判所での検認手続をしなくてはいけません。
「自筆証書遺言保管制度」を利用して法務局で保管してもらうと、家庭裁判所での検認手続が不要になります。
■ご利用料金(税込):55,000円+実費 (郵送費・書類取得費用など)
公正証書遺言の作成サポート
「公正証書遺言」とは、遺言者が遺言の内容を口頭で伝え、公証人が文章にまとめて作成するものです。
遺言者の伝えた内容が本人の真意であるか、公証人がまとめた文章に間違いがないか、2名以上の証人も参加し作成されます。
公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されるため、紛失・破棄・改ざんをされるリスクがありません。
また、家庭裁判所での検認手続も不要です。
公証人への手数料支払いが発生しますが、安全確実な遺言方法となっています。
■ご利用料金(税込):110,000円+実費 (郵送費・書類取得費用・公証人への手数料など)
⇒ 作成日当日、証人としての立ち合い料金を含みます。
遺産分割協議書の作成
「遺産分割協議書」とは、相続人全員の話し合いで決めた遺産分割の方法と相続の割合をまとめ、作成するものです。
作成には、相続人全員の署名と、実印の押印が必要です。
複数の相続人がいるのに遺言書がない場合、分割内容によるトラブル防止の場合に作成が必要です。
相続人が1人のみ場合や、遺言書の内容に沿って遺産分割をする場合など、作成不要なケースもあります。
■ご利用料金(税込):55,000円+実費 (郵送費・書類取得費用など)
財産目録の作成
「財産目録」とは、財産の内容がわかるよう一覧化したものです。
預金・不動産などのプラスの財産のほか、借金などのマイナスの財産も記載します。
■ご利用料金(税込):55,000円+実費 (郵送費・書類取得費用など)
相続関係説明図/法定相続情報一覧図の作成
「相続関係説明図」とは、被相続人の相続関係を図にまとめたものです。
必要事項の記載があれば、様式やその他記載事項について厳格なルールはありません。
「法定相続情報一覧図」は、被相続人の相続関係図について、法務局が間違いないことを証明してくれるものです。
相続手続のときに、戸籍謄本の代わりとして使用できます。
様式・記載内容などに厳格なルールがあり、申出書の準備や登記所への申出(郵送可)も別途必要です。
■ご利用料金(税込)
相続関係説明図:33,000円+実費 (郵送費・書類取得費用など)
法定相続情報一覧図:44,000円+実費 (郵送費・書類取得費用など)
遺言執行業務
「遺言執行」とは、遺言者の死後、遺言の内容を実現する手続きのことです。
遺言執行をする人を「遺言執行者」といい、遺言による指定または家庭裁判所への申立てによって選ばれます。
家庭裁判所への申立てをする際、業務についてほしい方がいれば、その方を候補者とすることも可能です。
遺言に以下のような事項が含まれているときには、遺言執行者の指定が必要です。
指定がない場合、家庭裁判所に申立てをして遺言執行者の選任をしてもらわなければいけません。
・遺言による認知(民法781条2項)
・推定相続人の廃除・廃除の取消(民法893、894条)
■ご利用料金(税込)
330,000円+実費 (郵送費・書類取得費用など)
【遺言・相続に関する業務】
下記のお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
原則ご連絡の翌日までにお返事させていただきます。
相談内容が不明ですとお返事できない場合がございます。
X(旧Twitter)のDMでもお問い合わせを受け付けています。